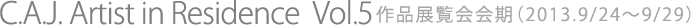





作る事は生きること
南條史生 森美術館館長
私がシンガポールのアートシーンに深く関わったのは、2006年にシンガポール・ビエンナーレの第一回目のディレクターに指名されてからのことである。その時に、まずシンガポールのアーティストと会ってみなければ、という強い思いで数十人のアーティストにインタビューをした。その中でもリー・ウエンとの出会いは思い出深い。彼は著名なアーティストだったので何しろ会って話してみよう、と連絡を取ったら、なんと日本で会うことになったのだ。
彼の仕事で一番知られているのはイエローマンのプロジェクトだろう。彼は体中を黄色に塗って、しばしば公共の場所に登場した。しかし彼のパフォーマンスはそれにとどまらない。その場の状況と呼応しながら、多様な展開を見せる。それは制度や現実との確執と苦悩、そして一個人の実存を表象する。2012年、シンガポールの国立美術館で、25年にわたる活動の集約とも言うべき大回顧展を開催したのは、そうした彼の制作の軌跡が高く評価されたからだろう。
ジェーソン・ウイは、極めてコンセプチュアルなアプローチで知られるシンガポールのアーティストで、インスタレーション、パフォーマンス、写真のプロジェクト等を発表してきた。シンガポール・ビエンナーレ2006では、旧市庁舎の裁判所の中で数十個のテレビ・モニターと黒板を使い、祖母の死とシンガポールの政治的な事件を結びつけた大型のインスタレーションを発表した。彼の作品の表現のスタイルは、毎回異なり、一つではない。しかし共通しているのは社会的・歴史的文脈の中で、今此所で我々が生きているのはどういうことか、何が可能なのかという問いかけに関わっていることであろう。
この二人が、CAJ-AIRに滞在し、現地の人々と関わり、交流を深めながら作品のインスピレーションを得たのは、日本にとってもシンガポールにとっても貴重な機会となった。一ヶ月を共にした二人の滞在の体験は、9月24日から9月29日までの展覧会に結実した。展示はジェーソンが撮った水面の写真、赤いドレスを着たリー・ウエンの屋外で行われたパフォーマンスの記録写真、秋山有徳大使の素描などを飯島のキュレーションで展示している。この展示は全体としてリー・ウエンとジェーソン・ウイ、飯島浩二、秋山祐徳太子との間でやりとりされた対話の記録だと言うことも出来るだろう。
展覧会開催の初日には、リー・ウエン、ジェイソン・ウイに飯島浩二氏を加えて、パフォーマンスが開催された。飯島は鉄の犬のしっぽでシンバルをたたき、リー・ウエンは黒いヴェールをかぶり床に横たわった。一方展覧会のクロージングでは、リー・ウエンが小さな音と伴にオルゴールと木の棒を振り回し、ヘルメットをかぶった秋山祐徳太子が能を演じてみせた。いずれにおいてもパフォーマンスの協同作業が表現の現場となった。展示を見るとパフォーマンスだけではなく、写真、素描、ヴィデオ、文字という様々なメディアが渾然一体となって滞在の成果をみせている。その成果を最終的にまとめたのが本書である。
アートは常にアーティストの様々な体験と思いの結実である。そしてそれは見る人にとっても、自分の人生と重ね合わせることができる多様な解釈の契機となる。シンガポールのアーティスト二人が埼玉でいかに暮らし、日本の人々とどのような交流をもち、何を表現しようとしたかということ自体がアートなのだ。その意味でアートは、生きることと同義であることを今更ながら、思わざるを得ない。アートするとは、永遠に向かって自らを投企することに他ならないのだ。















