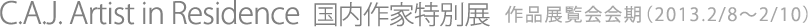


鉄の彫刻は終わったのか
藤井 匡(東京造形大学准教授)
鉄が彫刻素材の主流を占めた時代がある。20世紀後半のことだ。その状況を、ハーバート・リードは『近代彫刻史』(1965)において「新鉄器時代」と呼べそうなほどだと語っている。1930年頃にピカソとゴンザレスによって開始されたとされる鉄の熔接(構成)による彫刻は、近代都市や建築との親和性や素材の入手・加工の容易さによって、多くの彫刻家による幅広い展開を導く。もっとも、彫刻の価値基準を生命力の表現に置くリードはこの状況を認めることなく、近代彫刻の歴史は終わったと告げるのだが。しかし、その意向とは関係なく、その後の彫刻史は鉄を中心に進んでいくことになる。
だが、21世紀に入った現在、彫刻素材はさらに多様な方向へと広がり、鉄は中心的な位置を明け渡してしまう。それは、情報化に付随する生産様式の変化や、さまざまな素材を精密に加工できる機械の開発、テクノロジーの進歩など、現代社会そのものの変化に由来すると考えられる。さらにいえば、国際化の進展によって彫刻家の活動範囲が広がっていく中で、重量のある素材は運送の都合から不利益を被る可能性も出てきた。その結果、彫刻的な表現は立体物の範囲内における様式的な拡散に留まらず、映像や身体表現、アートプロジェクトなど形式的にも拡散していくことになったのだ。
本展に参加する5人は、これまでも鉄素材を中心に制作を行ってきた彫刻家である。当然のことながら、こうした事態と無関係でいることはできない。むしろ、時代の変化に自覚的だからこそ、本展のテーマに鉄が掲げられているのだろう。それは、以前から往々にして行われてきた、彫刻を素材別に分類・整理することを目的とした展覧会とは無縁である。「いま、なぜ鉄なのか。」そうした、表現の立脚点を問う批評的な視点から読まれなければならないと思われる。
彼らに共通するのは、大学生の時に、美術大学の授業カリキュラムで鉄という素材と熔接という技法に出会ったことである。だが、継承されたのはあくまで彫刻の素材・技法に限定される。現在の彼らの仕事は、20世紀後半の彫刻の造形観から大きくかけ離れているからだ。
悪戯的とも思える公共空間でのアクションを通して社会に批評的なメッセージを発信する飯島浩二。金属工芸の精密な加工技術と置物的な形式を用いて文化的な差異や違和をモデルとして提示する角文平。既製の自動車を豪快に回転させる非日常的なパフォーマンスによって祝祭空間をつくりだす久保田弘成。子どもの頃に見たアニメや特撮のヒーローをモチーフとして自身の世界観を大掛かりに展開する橘宣行。電動による無意味な動きを導入することで“もの”や“かたち”が日常的に所有している意味の脱構築を図るタムラサトル。
こうした仕事が、これまでの彫刻の形式的な価値観――形態・空間・量塊・表面・軸線など――に依存していないことは明らかである。それゆえ、これらが鉄を用いて制作されなければならない必然性も、本当のところは疑わしい。他の素材でも同様の表現が可能になる場合もあるはずである。逆に、鉄を素材とすることが合理的だと思えない場合だってあるのだ。「いま、なぜ鉄なのか。」だからこそ、この問題が深刻に問われなければな
らなくなる。
私の考えでは、彼らは美術や彫刻の価値観の推移を明確に自覚している。そして、新しい時代の価値観と自身のルーツとの落差を直視することを出発点に選んだのだ。決して、自由な表現を求めて鉄に到達したのではない。というよりも、誰だって自由な表現から出発することはできないのだ。過去は常に現在を拘束しようとする。前述した「批評的な視点」とは、不自由さを前提として自由を考えることを意味している。
価値観の推移を、リードがそうしたように、「終わった」の一言で片づけることは簡単だ。だが、理念ならば終わらせることもできるだろうが、生きることを終わらせることなどできはしない。それは、出発点として認識されなければならない。















