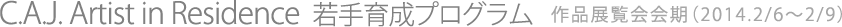





藤井匤(美術評論家/CAJ理事)
風景写真であるために/鈴木のぞみ
とりあえず、それを風景写真と呼んでみる。そのことによって何が見えるのか。蓋つきの鍋であっても箪笥の引き出しであっても、小さな穴が開いている箱は全てカメラの構造をもつ。鈴木のぞみはその画像を定着させることによって、そうした場所にも風景が存在することを提示する。ただし、そこに写るのは写真家が自由に選択したものではない。古い窓ガラスにそこから見える風景をプリントした作品も同様だ。画像は作者の主観を超えたところで決定されている。単に見えているものが風景と認識されるには、そこに意味を見出す人間の内面が必要となる(柄谷行人「風景の発見」)。だが、この作品が撮影者が意思をもって切り取った写真と異なるのは、鑑賞者の側の内面こそが必要だということである。事実、鈴木自身の姿勢を考えても、制作者よりも鑑賞者と呼ぶ方がふさわしいのかもしれない。こうした作品が記憶を喚起することは、鑑賞者は写真装置や被写体のみではなく、何よりも自身の内面と結びつくことで可能になる。
絵画空間の可能性/田神光季
田神光季の絵画は、インターネットで入手できる衛星写真をモチーフとしている。新しいテクノロジーが生みだす、時代のリアリティと密接に結びついた表現である。だが、重要なのは、そのことが絵画表現を決定的に左右しているのではないことだろう。作品として提示されるものは、平坦なキャンバスの上に絵筆で色をのせていく、伝統的な絵画の形式によっているからである。近接する形や色の関係、塗り重ねられる線や面の関係が複雑に構成されることから、オールオーヴァーな絵画空間が展開するのだ。モチーフは単にモチーフであり、最終的に画面に定着されるのは、作者というフィルターを通して変換された固有の表現となる。テクノロジーは進歩を続けていくはずだが、芸術が同様に進歩していく保障はどこにもない。絵画が歴史的に関わってきた課題とは、次々に解決されていく類のものではないからだ。限定された枠をもつ平面上で個の表現を成立させる絵画が、変わらずにもち続ける可能性に保障されるのである。
彫刻のパラドックス/茂木美里
透明なガラスであれば、その向こう側にあるものを見ることができる。周囲を写し込む鏡であれば、その表面にイリュージョンとしての空間が出現する。ここでは、そのようなモチーフを木彫で表現する際に生じるパラドックスが扱われている。見えているものと存在しているものがズレてしまう。それを解消するために、彫刻の表面に絵画的な要素が導入されるのだ。彫刻と絵画が折衷されるのではない。歴史的に形成されてきた彫刻表現の限界を考察することに淵源をもつのである。また、中原佑介は静物彫刻という言葉で彫刻のパラドックスを指摘したことがある。人間や動物なら問題はない。だが、木製の机をモチーフに木彫をつくると、彫刻自身も机として使えてしまう。モチーフと彫刻の差異が曖昧になるのだ。茂木美里が“彫刻らしく”見える形態や表面をあえて用いる理由はここにあるのだろう。彫刻の限界を超えるためには、彫刻に深く入り込まなければならないのだ。ここにもまた、彫刻のパラドックスが存在する。















