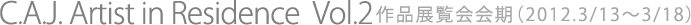




二人のメキシコの表現者―現実と民族誌的世界から
川崎市岡本太郎美術館 仲野泰生
私がメキシコに出会ったとき、メキシコはありとあらゆる多様な矛盾をかかえた姿で私の眼にうつり、私が自分の中に縺れた糸玉のようなものとして持ち続けてきたように思えた個々の線や特徴を、洗いざらい内側から外へ映写してくれたようなものであった。
(セルゲイ・M・エイゼンシュテイン『エイゼンシュテイン全集』1974年キネマ旬報社)
1920、30年代の欧米のアヴァンギャルドを指向するアーティストたちにとって、メキシコは彼らの憧れの地であった。例えば『戦艦ポチョムキン』(1925年)で映画史に名を刻んでいるセルゲイ・M・エイゼンシュテイン(1898-1948)もメキシコに憧れ、そして自分の中のメキシコ的なるものを発見した一人だ。そのエイゼンシュテインが最初に自身の表現としてメキシコ的なるものに関わったのがジャック・ロンドン原作の『メキシコ人』(1920年)の舞台上演で、彼は衣装と舞台装置を担当した。そしてメキシコとエイゼンシュテインの決定的な出会いが、メキシコ壁画運動の指導者の一人であったディエゴ・リベラとの出会いであり、その邂逅とメキシコへの旅が、彼の幻の名画『メキシコ万歳』(1930年)の制作
へと、エイゼンシュテインの中のメキシコ的なるものへの探求は繋がっていく。ところでエイゼンシュテインは、何故メキシコにこだわったのか。
当時、近代主義に限界を感じていたアーティストたちに刺激を与えたのが、欧米の植民地政策(アフリカ、中南米、オセアニア等)から生まれた学問・民族誌学であった。エイゼンシュテインも他のアーティストと同様、メキシコとの出会いに、彼の中の野性(民族誌学)とモダンな魂(アヴァンギャルド芸術)の交錯を発見したのではなかったろうか。
さてここまで描きながら私が、ふと思うのは、現在のメキシコは、エイゼンシュテインに影響を与えたような魅力を放っているのだろうかという事である。その一つの実証・答えとして、現代の日本の私たちに問いかけてくる二人のメキシコの表現者の展覧会が開かれる。
この二人とはメキシコのチアパス州で生まれたマヌエル・ベラスケスとベラクルス州在住の日本人・矢作隆一である。
ベラスケスは自分の中にあるメキシコを、スペインに征服される以前の時間とスペイン的なるもの(カソリック的なもの)を混在させながら、作品に現出させてきた。ベラスケスの制作はある意味で、彼のアイデンティティ探しといえる。作家自身の中に内包し、混合している歴史・時間を、彼独自のデリケートな色彩や単純化された形象と多層的なマチエールによって探求してきたといえるだろう。この探求は近代人・エイゼンシュテインの内なるメキシコ的なるものとしての自己発見と同様なものである。しかしエイゼンシュテインとベラスケスの決定的な差異は、ベラスケスが外側から見たメキシコではなく、彼自身の内包し、血肉化した身体を刻むことによってしかメキシコを確認できない作品であるということではないだろうか。ベラスケス自身の肉体ともいうべき作品について少し述べてみよう。彼の作品には、スペイン以前のメキシコの民話や伝説(動物、心臓、身体など)とスペインからもたらされた宗教であるカソリック(キリスト、教会、十字架など)が、モチーフとしてミックスされながら頻繁に登場する。そして最近ではモチーフがよりシンプルになり、強くなってきている。例えば絵画や立体で、不思議な空洞を持つ箱や美しい文様を持った種子となって現われてきた(今回の展覧会でも紹介されるであろう)。今回の作品はメキシコの一人のアーティストの原点探しの旅がたどり着いた一つの回答を見せてくれるに違いない。
もう一人のアーティストは、現在メキシコで活動をしている矢作隆一である。矢作は日本人としてメキシコで暮らす中で、制作を通してメキシコ的なるものに向かい合ってきた。彼の場合は、近代化され尽した日本に生まれ、日本でアーティストとしてスタートを切った。矢作はメキシコとは別の形で過去と現在が混在している日本で、「我々の在り方」(1994年)という個展を行いながら、現在の自分の表現基点たる位置を探していく。
その彼がメキシコで暮らし始めることで、テーマがより日常や生活そのものからの発想になったのである。彼は日本で暮らす中で日常に埋没していく自分ではなく、異質の時間が流れるメキシコの地で、日本人として仕事や家庭を持ち、毎日を過ごしていくことで感じた違和感と共感から『グアダルーペを探せ』のシリーズ等(メキシコの聖母伝説から生まれた名前を追うプロジェクト)を制作した。
私は今回の矢作の『瓦礫のじゅうたん―ガレキで花を咲かせましょう』の構想を彼自身の口から聞いたとき、この新作は日常や生活そのものから制作を続けてきた彼が、2011年3月11日の東日本大震災で、日常がいきなり非日常へと変わらざるを得なかった日本の現実を、メキシコから捉えた作品になるのではないかと思った。
メキシコには「アルフォンブラ デ アセリン」といっておが屑で道に絵を描く宗教行事がある。矢作はこのメキシコの宗教行事に習い、被災地の瓦礫で日本の象徴である桜を描くという。自然の脅威である地震で破壊された建物の瓦礫を、春に咲く桜(これも自然である)に変える作品は、日常が破壊されて非日常となった結果を、作品を通じて現出させることで、今の日本の現実を問う作品になるだろう。そして、この二人のメキシコからの表現者の作品を通じた問いかけに、答えていくのは日本の現実に暮らしている私たちでしかないのである。















